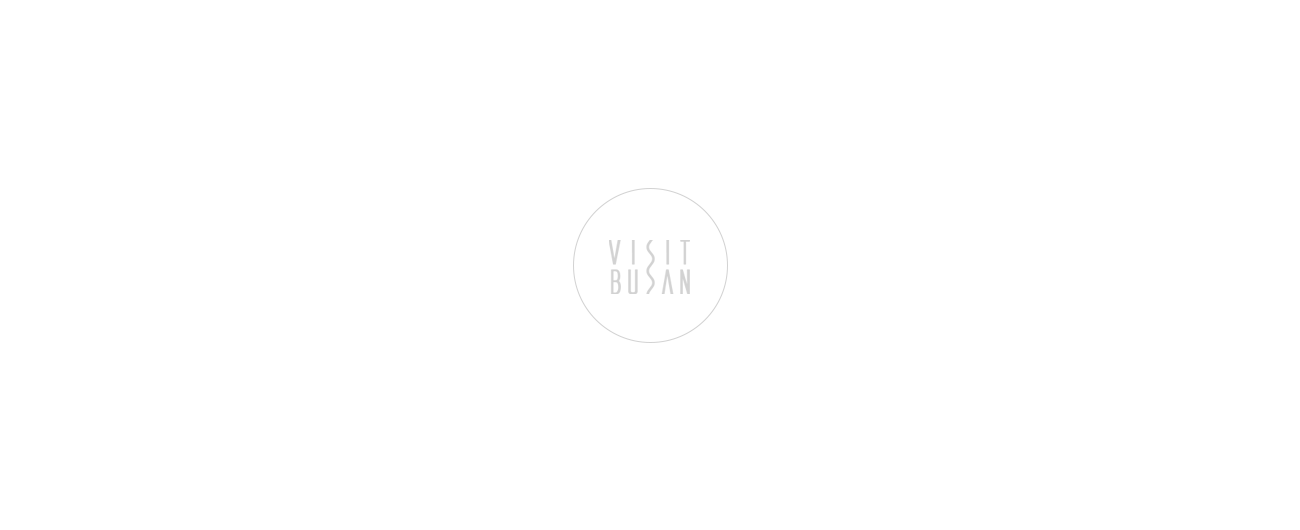
梵魚寺
金井山で鑑賞できる美しい寺院
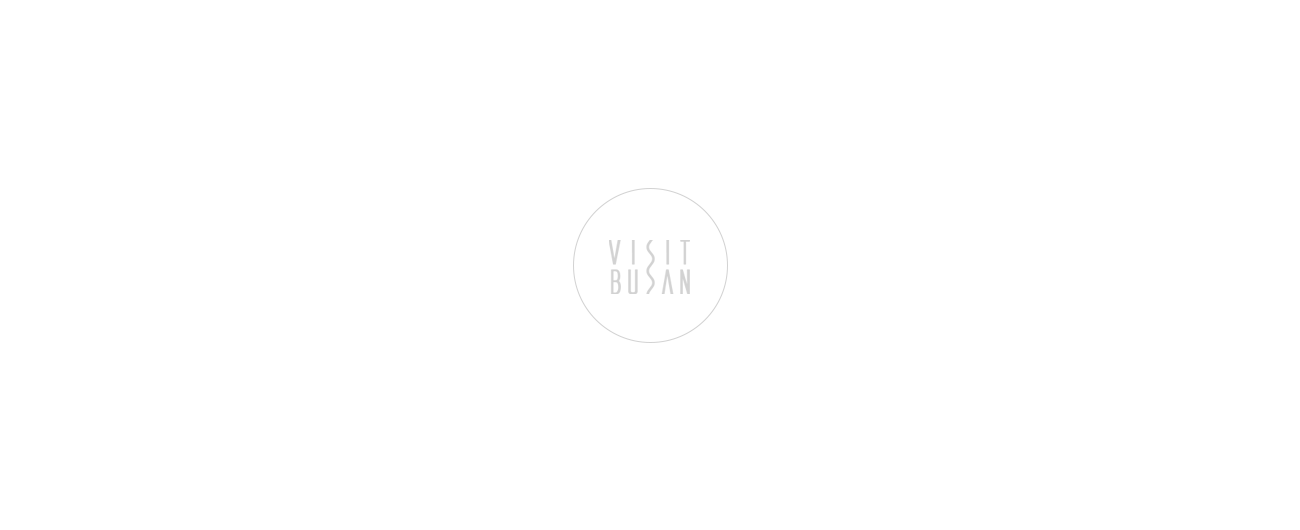
- 評価
 5.0
5.0 - PV 18,432
釜山市金井区にある梵魚寺は、海印寺、通度寺とともに嶺南三大寺院に名を連ねている。
新羅の文武王の時代に建立され、歴史的にも多くの高僧を輩出した修行寺院として有名。特に、美しい渓谷と自然で有名な金井山の麓にあり、一年を通じて多くの人々が足を運ぶ。
新羅の文武王の時代に建立され、歴史的にも多くの高僧を輩出した修行寺院として有名。特に、美しい渓谷と自然で有名な金井山の麓にあり、一年を通じて多くの人々が足を運ぶ。
梵魚寺の入口に足を踏み入れると、まず幢竿支柱と下馬石が目に入ってくる。1300年間この場所を守ってきた幢竿支柱は、このお寺の守護神のような存在だ。下馬石は、朝鮮時代後期、官吏たちの収奪に苦しんでいた僧侶たちの悩みを解決しようとの思いが込められた石像だそうだ。下馬石は書院や有名な宗宅の前にあるのをよく見かけるが、寺院にあるのはかなり珍しいケースである。
梵魚寺の曹渓門は、一柱門の役割をしている。身をかがめなければ通れないほど低くなっているが、常に謙虚な姿勢を持つべきという意味が込められているからだ。石柱と木柱で支えられている曹渓門は、朝鮮時代中期の建築様式となっており、当時の木造建築の研究において重要な史料となる。
宝物第434号に指定されている大雄殿は、端麗で堅牢な印象を受ける。軒を組む木材が全て丸い形に彫られていて、伝統美が感じられる。基壇の階段は、新羅時代の紋様と朝鮮時代後期の様式が混在する独特な形式となっている。大雄殿を一回りして、隠れた紋様を探してみるのも面白い。
大雄殿の内部は雄壮そのもの。宝物第1526号に指定されている木製の釈迦三尊像は、長い間その場所で慈しみ深い笑みを浮かべながら訪問客を迎えている。仏が暮らす仏土を表現した天井と仏画は荘厳な雰囲気を醸し出しており、まるで極楽浄土がそこにあるような感覚に陥る。
大雄殿の内部は雄壮そのもの。宝物第1526号に指定されている木製の釈迦三尊像は、長い間その場所で慈しみ深い笑みを浮かべながら訪問客を迎えている。仏が暮らす仏土を表現した天井と仏画は荘厳な雰囲気を醸し出しており、まるで極楽浄土がそこにあるような感覚に陥る。
梵魚寺のあちこちには、石で造られた遺物がたくさんある。大雄殿の入口にある石灯は統一新羅時代後期の様式を持ち、歴史的にも価値がある。礎に蓮の花が上下対称に表現されていて、たおやかで素朴な新羅の人々の美意識が感じられる。
宝物第250号に指定されている梵魚寺三層石塔にも、統一新羅時代の痕跡が見える。薄く平らな屋根石が水平になっていて安定感ある雰囲気を作り出しており、新羅時代の美をそのままに伝えている。
渓谷に沿って続く藤の群落でしばらく休んで行くのもいいだろう。まるであふれる水のように無数の石が集まっている「石の海」は、梵魚寺の名所とされる。緑の森の中で川のせせらぎに耳を傾けながらひと休みしていると、まるで仙人になったような気分が味わえる。
静かな山道に佇む美しいお寺、梵魚寺。
ふと癒されたいとき、余裕と休息のひと時を過ごせる場所だ。
ふと癒されたいとき、余裕と休息のひと時を過ごせる場所だ。
利用案内
住所
釜山広域市金井区梵魚寺路(ポモサロ)250電話番号
+82-51-508-3122ホームページ
http://www.beomeo.kr/eng_templestay/idt.php休業日
年中無休営業曜日及び時間
常時利用料金
無料交通情報
都市鉄道:1号線梵魚寺駅5、7番出口→90番バスに乗り換えて梵魚寺駐車場下車
駐車:梵魚寺駐車場(有料)
 障がい者専用駐車スペース
障がい者専用駐車スペース バリアフリー化粧室
バリアフリー化粧室
お役立ち情報
ホームページからテンプルステイの申し込みができる。
エチケット
僧侶の修行の場ですので、静かにご観覧ください。
関連タグ
おすすめ観光スポット










